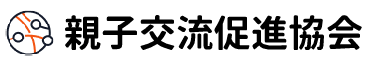ブログ
親子交流促進協会からお伝えしたいこと。
親子断絶をなくすために、みなさんと共有したい様々な情報を発信します。

家族法中間試案パブリックコメントに意見書を提出致しました
家族法制の見直しに関わる中間試案に足りない考察についての意見書 非常に意見を纏めるにあたっては悩みました。 特に海外で行われているDVがあったとされる親との親子交流については、 子供の聲を聴くことを訴えている為結論はなか

離婚前から親子交流の重要性を知る
当会の主事業は親子交流立会事業ではありますが、同時に親子交流の重要性をお伝えする活動も推進しております。 離婚後も別居して暮らす親との親子交流を継続することは容易ではなく、実施率は3割を切っています。 特に子供の年齢が高

子どもの聲(声)を聴く社会の実現
近年離婚の件数は増加の一途でそれに巻き込まれる子どもも増加の一途です。 離婚に面した子どもへの公共ケアは無いに等しい状況です。 離婚に面した子どもの聲は一緒に暮らす親が聴こうとしなければ、一切聴かれることはありません。

小牧こども未来館にて親子交流立会開始しました
皆さまお待たせしました。 立会員の他交流団体での立会研修を経ていよいよ小牧市こども未来館にて立会を開始致しました。 基本的に毎月最終日曜日の立会を予定しております。 こども未来館が午前午後の2部構成となっており、その時間
芸能人夫婦の子をめぐる争いに見るアドボカシーの必要性
昨今あびる優さんと才賀紀左衛門さん間や福永愛さん元夫婦間での子の引き渡しについてマスコミを巻き込んだ論争が続いています。 お互いが自分の正論を主張する姿を見ると日本の面会交流への否定的な状況の縮図だなと思い、お二人のお子

連れ去りには必ずビジネスが介在している
連れ去りは親一人だけではできません。必ずサポートする人間がいる。 弁護士、女性参画センター、児童相談所、生活安全課など数え上げるときりがない。 どれも利権、お金が絡み、家族を破壊することに何の躊躇もない人たち。 果たして
奈良子どもの権利条約9条を守る会は親子交流促進協会へ名称変更致しました
HP立ち上げ後のお知らせとなり大変申し訳ございません。 当会の名称は令和3年9月に変更となりました旨をお知らせいたします。 旧称でのチラシも一部配布中とのご指摘がありました為お詫び申し上げます。

一緒に暮らせなく(会えなく)なった親の存在を否定しなければならない子どもたちがいる事を。
子どもにとって両親はどちらも大切です。 しかしひとり親世帯の子にとって同居親は生活の全てです。 その同居親は別居親のことを口にはしません。 子が別居親のことを話そうとするとタブー視し、会話にも上げられません。 そうして片

離婚後の親子交流は同居する親の判断に全て委ねられ、誰も仲介できません
離婚後も離婚前も一度子どもと別居状態となると、子は同居する親側に忖度せざるを得ない状況になります。 それは10代の子どもでも同様で、同居する親側の意見に従ってしか子は別れて暮らす親に合う術はありません。 近年面会交流調停